
「ティール組織」の第一人者である嘉村賢州さん。
幅広く人が集うときに生まれる対立・しがらみを化学反応に変えるための知恵を研究し、まちづくりや教育などの非営利分野や、営利組織における組織開発やイノベーション支援など展開されています。弊社宮本と嘉村さんの対談をお届けします。

よろしくお願いします。

嘉村さんといえば「ティール組織」の第一人者というイメージですが、ティールと出会ったときって、「これはすごい!」と感じられたんでしょうか?

インターネットで見た海外のある記事がきっかけでした。その記事で紹介されていたティールの概要についてが半年間くらい忘れられなかったんです。いつもなら興味があってもすぐ忘れてしまうので、これは何かのメッセージだなと思い、ギリシャで行われた「ティール組織」のカンファレンスにすぐに参加しました。
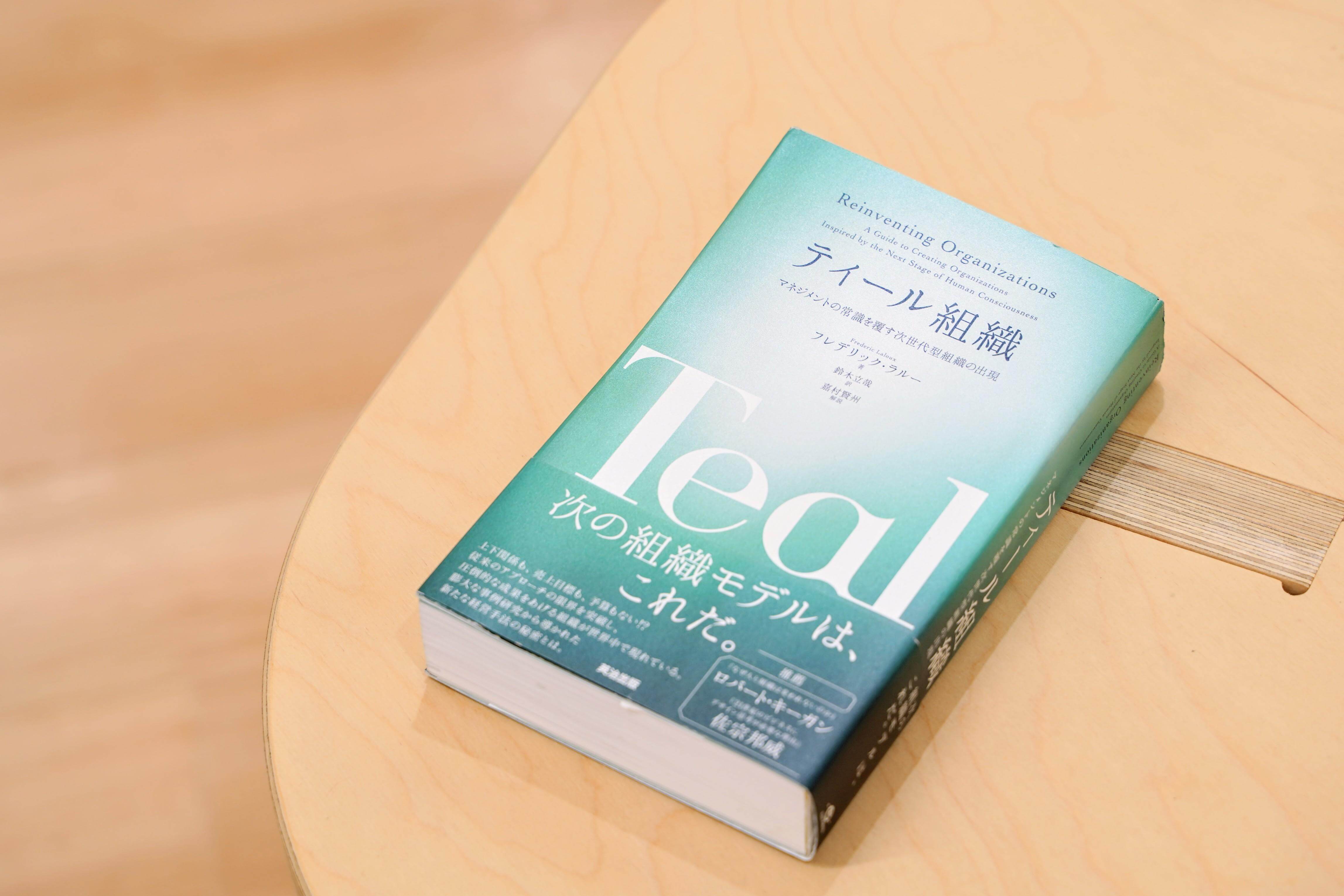
原書である『Reinventing Organizations』は2014年に出版。日本では2018年1月に出版
著者のフレデリック・ラルー氏は組織モデルを産業の発展・進化に紐づけて5つに分類、それぞれを色で表した。
レッド -> アンバー -> オレンジ -> グリーンと組織が進化していき、5番目にあたる最新型の組織モデルを「ティール色」(青緑色)と表現した。
・Red(レッド)組織 – 衝動的:圧倒的な力を持つトップが支配する組織
・Amber(アンバー)組織 – 衝動的:軍隊的なヒエラルキー組織
・Orange(オレンジ)組織 – 達成型:分権・柔軟性を伴う達成型組織
・Green(グリーン)組織 – 多元型:ボトムアップ型の組織
・Teal(ティール)組織 – 進化型:進化する組織
最も大きな特徴的は、ティール組織はレッド以降の進化を内包しているということ。ティール組織は、進化の過程で必要なものを組み込んだ結果、誕生する。
ティール組織、その本質とは?

日本でもティールに注目し始めている企業が出てきていると思いますが、積極的に導入している業界ってあるんでしょうか?

嘉村賢州(かむら・けんしゅう)1981年生まれ。兵庫県出身。京都大学農学部卒業。IT企業の営業経験後、 NPO法人「場とつながりラボhome’s vi」を立ち上げる。人が集うときに生まれる対立・しがらみを化学反応に変えるための知恵を研究・実践。2015年に1年間、仕事を休み世界を旅する。その中で新しい組織論の概念「ティール組織」と出会い、日本で組織や社会の進化をテーマに実践型の学びのコミュニティ「オグラボ(ORG LAB)」を設立、現在に至る。

本当にバラバラですね。大小かかわらず様々な企業が注目していると思います。

そうなんですね。従業員やマネージメントサイドなど、その人の立場によってティールに対する解釈も様々なように感じるのですが、ティールの本質ってどこにあるんでしょうか?

本質は二種類あると思います。
1つ目は、個々人が縦横無尽に動く生命体のように形態を変える組織であること、2つ目は、人が生まれてきた意味を見つけ、仕事を通して自分らしくそれを果していける組織ではないでしょうか。 本質とかけ離れているのは、階層構造を壊せばティール組織になるという考えです。表面的にマネージャーやリーダーを廃止してカオスになっている事例は多くあります。
HENNGEでの組織、そして ティールへの進化

なるほど。HENNGEの組織についてもお話させていただいてよろしいですか?

もちろんです。

HENNGEは23年前に3人の学生が立ち上げた会社で今はクラウドサービスを提供しています。組織を大まかに分けると、開発のチーム、セールスのチーム、製品サポートのチーム、管理部門のチームがあり、チームによって組織作りもそれぞれ異なっています。

1973年愛媛県生まれ。東京大学理科一類から文系に転向、文学部言語文化学科(国文学)卒業。 創業メンバーの一人としてHDE(現HENNGE)初期プロダクトのUI設計に従事し、97年11月の株式会社への組織変更をきっかけに代表取締役副社長に就任。 その後数年おきに直接部門と間接部門の行ったり来たりを繰り返し、現在はクラウドサービスの運用部門と人事部門を並行して担当。 部下を怒るのが大の苦手で、生まれてこの方一度も部下を怒ったことがない。最近なぜか「実はあの人は怖いらしい」という噂が流れていることを察知したが、都合がいいので噂はそのまま放置中。ここ数年で海外から来たメンバーも部下に入り、マネジメントは個人的にも会社的にも新しい局面に差し掛かっている。

それぞれどのような組織づくりをされているんですか?またメンバーの反応はどうでしょうか?

開発部門はティールに近いチーム作りをしていて、セールス部門はオレンジに近いです。製品サポートの部門はその中間のようなチームですね。

部門間でのコミュニケーションは上手く行っていますか?

意見が対立したり、交渉が必要なときに、互いの違いがなかなか理解できないということはあります…

両方の部門を兼任されている方とかっていらっしゃいませんか?

兼任があったほうがよいですか?

ティールを上手く活用しているところだと、複数役職大歓迎なんです。一人の人が複数の部門に属する、いわゆる兼任がよく見られます。
一部署に所属してしまうと、その部門最適なものの考え方になってしまう。なので、セールスとエンジニアどちらにも部分的に役割をもってみると一部門中心の考えではなく、会社全体として物事を見れるようになります。

なるほど、今はそのような立場の人はいないですね。
例えば、レッドに近い組織と、ティールのような組織どちらにも属した場合、その人自身が混乱するということはないでしょうか?

最初はコミュニケーションの違いで戸惑うこともあるかもしれませんが、兼任することでそれぞれの組織のメリットを知り、片方の組織によりよい影響を与えることも起こりえると思います。

兼任はスタッフレベル、マネージメントレベルどちらでも効果がでますか?

はい。ただそもそもティールにはマネージャーという概念が存在しないので。

確かにそうですね。

マネージャー、リーダーとは何かと言うと、結果責任と命令権限を与えることです。オレンジの組織では、経営の立場からするとマネージャーを置いた方が統率が取りやすいんですが、弊害が生まれます。リーダーやマネージャーは役割が多すぎて、かつそれがブラックボックスになりやすい。
なので、リーダーを置かずに役割をはっきりさせた上で、それを様々な人に分散させるのがホラクラシー的考え方ですね。例えば、顧客対応をしつつ開発のアイディアにも関わるなど、さらに役割を兼任することで、一部署中心的な組織では無くなります。

そこまでたどり着くのは、なかなかしんどそうですが…するために入れています。

そのとおりです。
すぐに階層構造を壊そうとせず、まずは「結果責任と命令権限を抱えているマネージャーの役割を明確にした上で、それを最低限にしていく」ということから緩やかにティールに近づけていくのがいいのではないでしょうか。

そこが課題になりそうですね。部署によって組織形態が違うことによるマネージメントの仕方を責め合ったりすることも起こりうると思うのですが、その点はどのように折り合っていけばよいでしょうか?

どうしてもアンバーの考え方(業務プロセスを明確にする)、オレンジの考え方(リノベーションを求める)、グリーンの考え方(みんなで話し合って決める)はそれぞれが牽制しあってしまうんです。
ただ、ティールは一つの考え方が優れているのではなく、すべての考え方に価値があるという考え方なんです。会社全体で、すべての考え方がかみ合うように、御社流に作り上げていくのがよいと思います。


なるほど、それぞれのチームの良さを活かしながら、全体の組織づくりに生かしていけばいいのですね。

そのとおりです。
変化の早い組織での ティール組織への道のり

一般的に新製品を開発する際に、プロダクトサイクルと言われるものがありますよね。私たちはITなので、このサイクルが2〜3年で一巡するんです。
経験則から、最初の新しい製品を生み出す時には、みんなが意見を出して上下関係がないフラットな組織が上手く機能し、商品が売れ始めると割とピラミッド形の安定した組織の方が上手くいくような気がしています。HENNGEも23年間、この組織を行ったりきたりしてきたような感じです。
ただ、組織の移行のフェーズで、ピラミッド型のマネージメント層にいた人がフラットな組織になったときに順応できないという問題も起こっている気がしています。

なるほど。

今後も新しいプロダクトを作り続けていくためには、ピラミッド型の組織、フラットな組織どちらにも柔軟に対応できる人材がキーになっていくのかなと思っています。ただ、ピラミッド型の組織の上の方にいた人が、フラットな組織に行くことはなかなか難しいのが現状です。


それは、仕事量的に行きたくてもいけないのでしょうか。それとも、挑戦したいという気持ちが起こらないのでしょうか?

一概には言えなくて、それぞれの理由があるように感じています。

今後の採用にも大きく関わってきそうですね。入社前に、御社には二種類の組織が存在して、どちらにも価値を見いだせるキャリアパスを描くように導いてく。 また、評価制度も組織に関わらず平等に評価される仕組みが必要になりますね。

わかりました!
様々な国々でのティール組織の馴染みやすさ

最後に、弊社には今2割くらい外国籍の社員がいるのですが、ティール組織に馴染みやすい国柄ってあるのでしょうか?

個人に目標設定をさせる教育をしているオランダや北欧は馴染みやすいと思います。次にアメリカなどでしょうか。この国の人には馴染まないというのはありません。

ちなみに日本人はどちらかといえば馴染みにくいのでしょうか?

個人主義的な面が強い欧米と比べると、ホールネス(全体主義)的な点では日本人は優れているので向いていると言えますね。人のために貢献したいという欲求も強いのでティール組織に向いている要素です。
ただ、向いていない点も2つあります。1つ目は、異端児になりずらい、輪を乱せないところですね。自由に考えてもいいといわれても、何か答えがあるのではないかと考えてしまったり、他の人からの承認を得ないと動き出せないという性質があります。2つ目は、物事を明文化したがらない点です。ティールでは、お互いの認識をすり合わせて言語化することが重要になってくるので、その点は意識して行わなければならない点です。

これまでの日本の教育の結果とも考えられますね。

そうですね。点数主義や受験の早期化はビジネス社会の流れとは逆行しているように思います。
子どもの頃に夢中になった経験がある人ほど、社会人になっても夢中になれると言われています。そうゆう点で、日本の教育も変わっていくといいですね。

教育もビジネスも主体的に輝いていける人が増えていくことを願いたいですね。

そのとおりだと思います。

本日は、どうもありがとうございました!

初めまして、今日はどうぞよろしくお願いします。